「大日本武道宣揚会」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
| 63行目: | 63行目: | ||
[[天恩郷]]の仮道場での武術講習や全国各地への巡回講師の派遣などによって、大日本武道宣揚会の発足から半年の間に、支部は50ヶ所、会員は1500人となった。会員の増加により仮道場では手狭となり、新道場の建築計画が進んだ。ところが突然、王仁三郎の意向によってその計画が変更され、大日本武道宣揚会総本部と道場が竹田に移転することになった。それは[[竹田別院]]に、道場に転用できる建物が存在していたからである。<ref>『[[竹田別院五十年誌]]』138頁</ref> | [[天恩郷]]の仮道場での武術講習や全国各地への巡回講師の派遣などによって、大日本武道宣揚会の発足から半年の間に、支部は50ヶ所、会員は1500人となった。会員の増加により仮道場では手狭となり、新道場の建築計画が進んだ。ところが突然、王仁三郎の意向によってその計画が変更され、大日本武道宣揚会総本部と道場が竹田に移転することになった。それは[[竹田別院]]に、道場に転用できる建物が存在していたからである。<ref>『[[竹田別院五十年誌]]』138頁</ref> | ||
昭和7年(1932年)8月5日、兵庫県朝来郡竹田町竹田(現・朝来市和田山町竹田)にある虎臥城(とらふすじょう。現・竹田城<ref>現在は「天空の城」として有名。</ref>)城址を所有していた竹田町から大本へ、城趾が献納された<ref>竹田での大本宣教が始まったのは昭和6年12月16日であり、すでにその頃から竹田町側から城址献納に向けた動きはあった。『[[竹田別院五十年誌]]』41~44頁・614~615頁</ref>。10月18日、王仁三郎と二代澄子は虎臥城に登り、王仁三郎は城址を「[[愛善郷]]」と命名した。<ref>『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c5227|諸運動の展開}}」</ref> <ref>昭和7年5月16日(五十年誌8頁、615頁では5月16日。七十年史では4月16日。おそらく前者が正しい)、竹田町に[[人類愛善会]]の支部が設置され、全町内400戸が会員となった。それにより虎臥城が大本に献納される話が持ち上がった。7年7月19日に出口宇知麿が竹田町へ行き町長・町議らと協議して、献納が決まった。大日本武道宣揚会設立と虎臥城献納は直接関係はないが、同じ時期に平行して話が進んでいたことになる。</ref> | |||
10月18日に王仁三郎夫妻が宿泊した場所は虎臥城の麓にあり、旧石原本家と呼ばれる町一番の宏壮な邸宅だった。朝来銀行の所有になっていたが、王仁三郎の指示で大本がここを買い取り、12月24日に大本[[竹田別院]]が設置された。<ref>『[[竹田別院五十年誌]]』10頁・98~106頁。昭和7年現在の旧石原本家の平面略図が102頁にある。</ref> | |||
昭和8年(1933年)3月30日、愛善郷の地鎮祭が城址で執行された際、王仁三郎は竹田別院(旧石原本家)を検分し、「別院の建物あまり多ければ武術の道場に使用せんとす」と歌を詠んだ。天恩郷に新道場を建築する計画が進んでいたが、竹田に適した建物があったため、ここに大日本武道宣揚会の総本部と道場を移転することになった。<ref>『[[竹田別院五十年誌]]』138頁</ref> | 昭和8年(1933年)3月30日、愛善郷の地鎮祭が城址で執行された際、王仁三郎は竹田別院(旧石原本家)を検分し、「別院の建物あまり多ければ武術の道場に使用せんとす」と歌を詠んだ。天恩郷に新道場を建築する計画が進んでいたが、竹田に適した建物があったため、ここに大日本武道宣揚会の総本部と道場を移転することになった。<ref>『[[竹田別院五十年誌]]』138頁</ref> | ||
2025年4月11日 (金) 10:37時点における版
大日本武道宣揚会(だいにほんぶどうせんようかい)は、大本の外郭団体。昭和7年に出口王仁三郎が総裁、植芝盛平が会長となり発足。〈建国の大精神に基き大日本武道の宣揚を為す〉ことが目的[1]。合気武術の修練を主とし、併せて剣道の修行も行った[2]。第二次大本事件によって大本8団体は結社禁止処分となり本会も解散した[3]。
略史

昭和6年(1931年)10月18日(旧9月8日[4])、昭和青年会が全国統一組織となり[5]、天恩郷に本部が置かれ、組織の一つとして「武術部」が設置された[6]。武術部主任に植芝守高(植芝盛平。当時48歳)が任命され[7]、翌7年4月12日[8]には天恩郷に仮道場を設けて武術の稽古が行われるようになった[9]。この昭和青年会武術部が、修行者が増えるにつれ独立の要望が高まり、大日本武道宣揚会が発足することになる[9]。
昭和7年(1932年)7月、「大日本武道普及会」という名称で〈全国的に惟神の武道の普及を図る〉[10]団体が設立されることが発表される。[11]
しかしこの構想は王仁三郎の指示により〈独立したものを作らず昭和青年会武術部を延長して其支部を各地に設置する〉[12]ことになった。
だが結局、「大日本武道宣揚会」という名称で、昭和青年会から独立した団体として設立されることになった。[13] [14] [15]
昭和7年(1932年)8月13日(旧7月12日)聖師生誕祭の日に大日本武道宣揚会が発足する[16]。総裁・出口王仁三郎、総裁補・出口宇知麿、会長・植芝守高。顧問には出口日出麿、蓮井継太郎(大日本国粋会理事)、中山博道(剣道範士)、二木謙三(医学博士)、三浦真(陸軍少将)が就任した[17] [18]。
7年11月2日(10月30日から始まる大本大祭第四日)、天恩郷で大日本武道宣揚会の第一回総会が開催される。[19] [20]
昭和8年(1933年)1月1日、会旗が制定される。会則が改訂される。[19]
8年5月1日、大日本武道宣揚会の総本部が亀岡天恩郷から但馬竹田の愛善郷(竹田城址)へ移る。[19]
8年11月5日、綾部に道場が完成する。[19]
昭和10年(1935年)7月1日、植芝に代わり出口日出麿が会長に就任。植芝は「範主」として武道の指導に当たることになる。[21] [19]
昭和11年(1936年)3月13日、当局は大本8団体に解散命令を出し、大日本武道宣揚会は解散した。
活動
会則第二条に本会の目的は〈建国の大精神に基き大日本武道の宣揚を為す〉ことだと記されている。ここでの「建国の大精神」とは次の趣意書や紹介文から推測すると「皇道」だと思われる。真の武道は皇道を体現したものであり、それは植芝盛平の「相生流合気武術」即ち合気道だということになる。
【趣意書抜粋】[22]
神国日本の武道は惟神の道こそ真の武道大道より発して皇道を世界に実行する為に、大和魂の誠を体に描き出したものである。(略)
今や天運循還、百度維新、東西古今の文物は翕然《きゅうぜん》として神洲帝国に糾合され、世界人は斉しく神機の大なる発動を待望して居る。しかしてこの混沌たる世界を救うの道はただ日本固有の大精神たる皇道を天下に実行するのほか無いのである。
わが大日本武道は神の経綸、皇道の実現のために惟神の人体に表されたるものであって、蔵すれば武無きが如く、発すればよく万に当る兵法の極意を尽すものである。
昭和維新の大業は政治経済のみでもゆかず学術のみでもゆかず、また精神のみでも充分ではない。われわれは神より下されたる真正の大日本武道を天下に宣揚してこの大業成就の万分の一の働きを|相《あい》共にさして頂きたいのである。神より発したものは神に帰る。
真の武は神国を守り、世界を安らけく、人類に平和をもたらすものである。(略)【大本刊行物に記された紹介文】[22]
大日本武道宣揚会はこれまた昭和青年会と兄弟の関係にあり、出口王仁三郎師を総裁に推戴し、建国の大精神に基づき大日本武道の宣揚を為すを以て目的とする。
そもそも真正の武は大神の神勇の発現であって、その背後には必ず神愛と神智と神親とが伴っている。故に人を殺し敵を亡ぼさんが為にこれを用うるに非ずして、人を生かし敵を改過遷善せしむるが為にこれを用い、更に大にしては国を活かし世を救うが為にこれを行使するものである。(略)
大日本武道宣揚会はこの本義に則り、真正なる大日本武道即ち神より出づる武道の宣揚に精進しているのである。
現在本会においては会長植芝守高氏の大神より神授せられたる相生流合気武術を主として修練し、軍部方面にも大いに歓迎せられ、非常時日本に大なる貢献を致しつつあるが、更に武道の各方面に及ぼす事となっている。(略)植芝は大正9年(1920年)大本に入信し綾部に移住して武術の道場(植芝塾)を開いた。昭和2年(1927年)綾部から東京へ一家をあげて移住[23]。同6年4月、東京の新宿・若松町にはじめて本格的な合気道場(皇武館、現・合気会)を開いた[24]。東京移住後は大本との関係が薄れていた[25]が、王仁三郎の要請によって同7年8月、大日本武道宣揚会会長に就任。亀岡でも合気武術を教えることになった。
大日本武道宣揚会では道士、宣士、助士という称号を設け[26]、武術の教授を行わせた。[27]
天恩郷の仮道場での武術講習や全国各地への巡回講師の派遣などによって、大日本武道宣揚会の発足から半年の間に、支部は50ヶ所、会員は1500人となった。会員の増加により仮道場では手狭となり、新道場の建築計画が進んだ。ところが突然、王仁三郎の意向によってその計画が変更され、大日本武道宣揚会総本部と道場が竹田に移転することになった。それは竹田別院に、道場に転用できる建物が存在していたからである。[28]
昭和7年(1932年)8月5日、兵庫県朝来郡竹田町竹田(現・朝来市和田山町竹田)にある虎臥城(とらふすじょう。現・竹田城[29])城址を所有していた竹田町から大本へ、城趾が献納された[30]。10月18日、王仁三郎と二代澄子は虎臥城に登り、王仁三郎は城址を「愛善郷」と命名した。[31] [32]
10月18日に王仁三郎夫妻が宿泊した場所は虎臥城の麓にあり、旧石原本家と呼ばれる町一番の宏壮な邸宅だった。朝来銀行の所有になっていたが、王仁三郎の指示で大本がここを買い取り、12月24日に大本竹田別院が設置された。[33]
昭和8年(1933年)3月30日、愛善郷の地鎮祭が城址で執行された際、王仁三郎は竹田別院(旧石原本家)を検分し、「別院の建物あまり多ければ武術の道場に使用せんとす」と歌を詠んだ。天恩郷に新道場を建築する計画が進んでいたが、竹田に適した建物があったため、ここに大日本武道宣揚会の総本部と道場を移転することになった。[34]
8年5月1日に竹田に移転した後も大日本武道宣揚会の活動は盛況で、常時50~60人がここで寝泊まりして「武農一如」の道場生活を送った[35]。自給自足の集団生活である。移転後半年の間に本部と支部で87回もの講習会を行い、受講者はのべ2278人にのぼり、8年12月末には支部129ヶ所、会員2488人へと拡大した[36]。
また要請があれば、各地の憲兵隊・海軍大学・警察・在郷軍人会・中学校などでも講習会を開いて指導にあたった[37]。
急速に発展する一方で、内部的に深刻な問題が発生していた。大日本武道宣揚会は昭和青年会武術部を端緒としており、大本の外郭団体であって、単なる武術の道場ではない。趣意書などから窺い知れるように、王仁三郎の皇道宣布活動の一翼を担っていた。植芝自身は大本信者だが、植芝の弟子たちは必ずしも信者ではなく、武術の鍛錬に重きを置く者が多かった。そのため、信仰重視の信者たちと、植芝の弟子たちの間に軋轢が生じたのである。植芝吉祥丸によると〈指導陣も大本とは全く無関係の内弟子たちによって占められ、実質的には開祖(編注・植芝盛平)個人の、つまり皇武館支部道場のごとき観を呈した〉[38]。〈会自体はそのような組織体(編注・大本の外郭団体)であったにもかかわらず、実際には、合気道の修行道場としての「竹田道場」の存在のほうがむしろ主となり、会は従のごとき印象をうけるようになっていった。いいかえれば「竹田道場」は、東の牛込若松町〝地獄道場〟(編注・新宿の皇武館)に呼応する西の〝地獄道場〟とでもいうべき、合気道隆盛の一大拠点のありさまになってゆく〉[39]。
昭和8年12月から翌年3月にかけて、大日本武道宣揚会幹部と大本幹部が集まり、「武宣(大日本武道宣揚会)の今後の運動発展」について懇談会がもたれが、結局「従来のまま」ということで決着した[40]。
会勢は快調に進展し、国外へも講師を派遣した。昭和9年4月の総会では会員5千人、受講者総数7千人と発表された。しかし〈霊体一如の修練を目的とした創立の精神から逸脱した、一部講師の行為は放置できない状況となった。かつて出口聖師が「大日本武道宣揚会の武道というものは、肩をそびやかしたり腕をまくるのでなく、肩を下げて地蔵さんのような肩になって、愛善の精神をもってやってもらいたい」と注意を与えていたが、竹田においてもその腕っぷしをかわれたエピソードがたえず(略)武勇談などが語りつがれている〉という状況だった。[41]
昭和10年7月1日、役員人事が更迭され、会長には植芝の代わりに出口日出麿が就任し、植芝は「範主」として武道の指導にあたることになった[21]。これによって第二次大本事件の際、植芝は警察に事情聴取はされたものの、検挙されることはなかった。〈植芝氏は会長職をはなれていたこと、弟子のなかに、官憲や上層部関係者がいたことが幸いしたものと思われる〉[42] [43]。
10年10月31日(27日から始まった大本大祭の5日目)天恩郷で大日本武道宣揚会主催の奉納武道大会が約3時間半に亘り盛大に開催され、植芝範主による合気武術の解説・実演や、剣道・気合術・杖術の試合などが行われた[44] [37] [45] [46]。(これが大日本武道宣揚会の対外的活動の最後になったようである[47])
昭和11年(1936年)3月13日、当局の命令により大日本武道宣揚会は解散した(「大本八団体」参照)。だが植芝盛平の活動は進展し、昭和15年4月には「財団法人皇武会」となり、昭和23年2には「財団法人合気会」と改称して合気道を大成させて行く。
参考文献
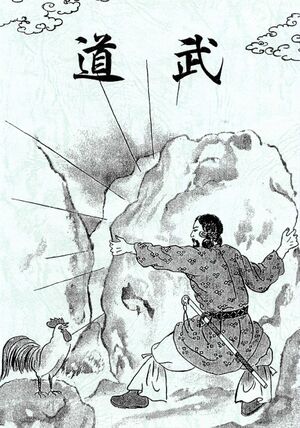
- 大本の機関誌『真如の光』昭和7年(1932年)11月15日号、88頁に第一回総会における王仁三郎の講話が、91頁に副会長の神本泰昭による「開会の辞」が掲載されている。王仁三郎の講話は『出口王仁三郎全集 第1巻』453頁「文武の日本#」に転載されている。
- 『皇道大本事務便覧』昭和8年(1933年)3月、139~152頁「大日本武道宣揚会趣意書」「大日本武道宣揚会会則」(昭和8年1月1日改正)、NDLDL蔵書 PID:1137512/1/88
- 芦田万象『救世と皇道大本』昭和8年(1933年)8月、98~99頁「大日本武道宣揚会」:当時の大本の大日本武道宣揚会に関する公式プロフィール。NDLDL蔵書 PID:1137376/1/53
- 有留弘泰『皇道の栞』第4版、昭和9年(1934年)6月、481~484頁「大日本武道宣揚会」:当時の大本の大日本武道宣揚会に関する公式プロフィール。NDLDL蔵書 PID:1111754/1/268
- 大日本武道宣揚会の機関誌『武道』昭和8年(1933年)7月号・11月号(第7号)(八幡書店の復刻版)
- 『大本竹田別院五十年誌』昭和62年(1987年)、136~144頁「大日本武道宣揚会」:大日本武道宣揚会の活動(特に竹田での活動)について詳しく記されている。
- 広瀬浩二郎『人間解放の福祉論』平成13年(2001年)、137~159頁「第四章 大日本武道宣揚会がめざした神武《しんぶ》の普遍化 ─合気道と親英(親和)体道の歴史を中心に─」:植芝盛平の生い立ちから大東流柔術の修行、王仁三郎との出会い、大日本武道宣揚会での活動など合気道の成立へ至る過程が詳しくまとめられている。
- 『大本七十年史 下巻』
- 大本年表
以下の本には植芝盛平サイドから見た大日本武道宣揚会の姿が記されている。
- 植芝吉祥丸『合気道開祖 植芝盛平伝』昭和52年(1977年)、217~225頁「武道宣揚会・竹田道場」・226~232頁「忘れがたき恩人」
- 砂泊兼基『合気道開祖植芝盛平伝 武の真人』昭和56年(1981年)、165~174頁「大日本武道宣揚会」「道場の生活」
関連項目
外部リンク
脚注
- ↑ 会則第2条
- ↑ 『竹田別院五十年誌』137頁
- ↑ 治安警察法第8条第2項による。
- ↑ この年の新9月8日には本宮山山頂に神声碑等3つの石碑が建立された。
- ↑ 昭和青年会は昭和4年に結成されたが、全国統一組織ではなく、各地方ごとに組織され活動していた。
- ↑ 『大本七十年史 下巻』「昭和青年会の改組#」
- ↑ 『昭和青年』昭和7年1月号78頁に記載あり。
- ↑ 『人類愛善新聞』昭和7年7月下旬号(7月23日発行)3頁〈亀岡総本部では武術部道場が四月十二日に開設〉
- ↑ 9.0 9.1 『竹田別院五十年誌』136頁
- ↑ 『真如の光』昭和7年7月5日号の記事「武術部より」(『壬申日記 7の巻』70頁に転載されている。NDLDL蔵書 PID:1137838/1/47)
- ↑ 『人類愛善新聞』昭和7年7月下旬号(7月23日発行)3頁〈近く相生流を主体に大日本武道普及会を創設する運動が(略)提唱されてゐる〉
- ↑ 『真如の光』昭和7年7月15日号の記事「武術部より」(『壬申日記 7の巻』173頁に転載されている。NDLDL蔵書 PID:1137838/1/103)
- ↑ 『中外日報』昭和7年7月21日掲載記事(『壬申日記 7の巻』256頁に転載されている。NDLDL蔵書 PID:1137838/1/147)
- ↑ 『北国夕刊新聞』昭和7年(1932年)7月26日掲載記事(『壬申日記 7の巻』307頁に転載されている。NDLDL蔵書 PID:1137838/1/172)
- ↑ 『真如の光』昭和7年8月5日号の記事「武術部より」(『壬申日記 7の巻』301頁に転載されている。NDLDL蔵書 PID:1137838/1/103)に次の記載がある。〈植芝守高氏は生誕祭(編注・8月13日の聖師生誕祭)の前後各一週間、天恩郷の道場に於て『相気武術会』なるものを創立する事を許され、会長(編注・王仁三郎)は総裁となり、宇知麿氏総裁補、植芝守高氏会長に決定し、他は適当に実施すべき旨(編注・が王仁三郎から)お示しがあった。〉これは二週間だけの限定の会ということか?
- ↑ 『出口王仁三郎全集 第八巻』610頁の年表に〈八月十三日大日本武道宣揚会創立。〉とあるので、公式にはこの日が創立日のようである。ただしそれ以前に設立されていたかのような記事も散見する。『人類愛善新聞』昭和7年8月上旬号(8月3日発行)3頁には〈七月下旬号に予告した大日本武道普及会は七月十八日を以て亀岡総本部に日本武道宣揚会として設置された〉とある。『北国夕刊新聞』7月26日号の記事や、『参陽新報』7月26日の記事(『壬申日記 7の巻』308頁に転載されている。NDLDL蔵書 PID:1137838/1/173)は、会が結成されたことが過去形で報道されている。「大本年表」の昭和7年7月26日の項に〈大日本武道宣揚会創立。聖師を総裁に植芝守高を会長として8・13発足。〉と記されているが、なぜ7月26日の項に記されているのか理由がよく分からない。前述の新聞の発行日か?
- ↑ 『竹田別院五十年誌』137頁
- ↑ 『真如の光』昭和7年11月15日号92頁〈中山博道氏、二木謙三氏、蓮井継太郎氏、三浦真氏等一流の大家名士が顧問となつて居られ〉
- ↑ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 「大本年表」
- ↑ 『真如の光』昭和7年11月15日号13頁。
- ↑ 21.0 21.1 『竹田別院五十年誌』143頁、618頁
- ↑ 22.0 22.1 現代仮名遣いに修正した
- ↑ 植芝吉祥丸『植芝盛平伝』192頁
- ↑ 植芝吉祥丸『植芝盛平伝』208頁
- ↑ 植芝吉祥丸『植芝盛平伝』217頁
- ↑ 会則第7条
- ↑ 政府の外郭団体である大日本武徳会では範士、教士、錬士という称号を用いている。大日本武徳会 - ウィキペディア
- ↑ 『竹田別院五十年誌』138頁
- ↑ 現在は「天空の城」として有名。
- ↑ 竹田での大本宣教が始まったのは昭和6年12月16日であり、すでにその頃から竹田町側から城址献納に向けた動きはあった。『竹田別院五十年誌』41~44頁・614~615頁
- ↑ 『大本七十年史 下巻』「諸運動の展開#」
- ↑ 昭和7年5月16日(五十年誌8頁、615頁では5月16日。七十年史では4月16日。おそらく前者が正しい)、竹田町に人類愛善会の支部が設置され、全町内400戸が会員となった。それにより虎臥城が大本に献納される話が持ち上がった。7年7月19日に出口宇知麿が竹田町へ行き町長・町議らと協議して、献納が決まった。大日本武道宣揚会設立と虎臥城献納は直接関係はないが、同じ時期に平行して話が進んでいたことになる。
- ↑ 『竹田別院五十年誌』10頁・98~106頁。昭和7年現在の旧石原本家の平面略図が102頁にある。
- ↑ 『竹田別院五十年誌』138頁
- ↑ 植芝吉祥丸『植芝盛平伝』221頁
- ↑ 『竹田別院五十年誌』141頁
- ↑ 37.0 37.1 『大本七十年史 下巻』「諸団体の活動#」
- ↑ 植芝吉祥丸『植芝盛平伝』217頁
- ↑ 植芝吉祥丸『植芝盛平伝』219~220頁
- ↑ 『竹田別院五十年誌』142頁
- ↑ 『竹田別院五十年誌』142頁
- ↑ 『竹田別院五十年誌』164~165頁
- ↑ 『植芝盛平伝』226~232頁
- ↑ 『真如の光』昭和10年11月17・25日合併号15~17頁
- ↑ 『竹田別院五十年誌』144頁
- ↑ この日、天恩郷の明光殿にて第一回歌祭が開催されている。
- ↑ 広瀬浩二郎『人間解放の福祉論』149頁の最後の行